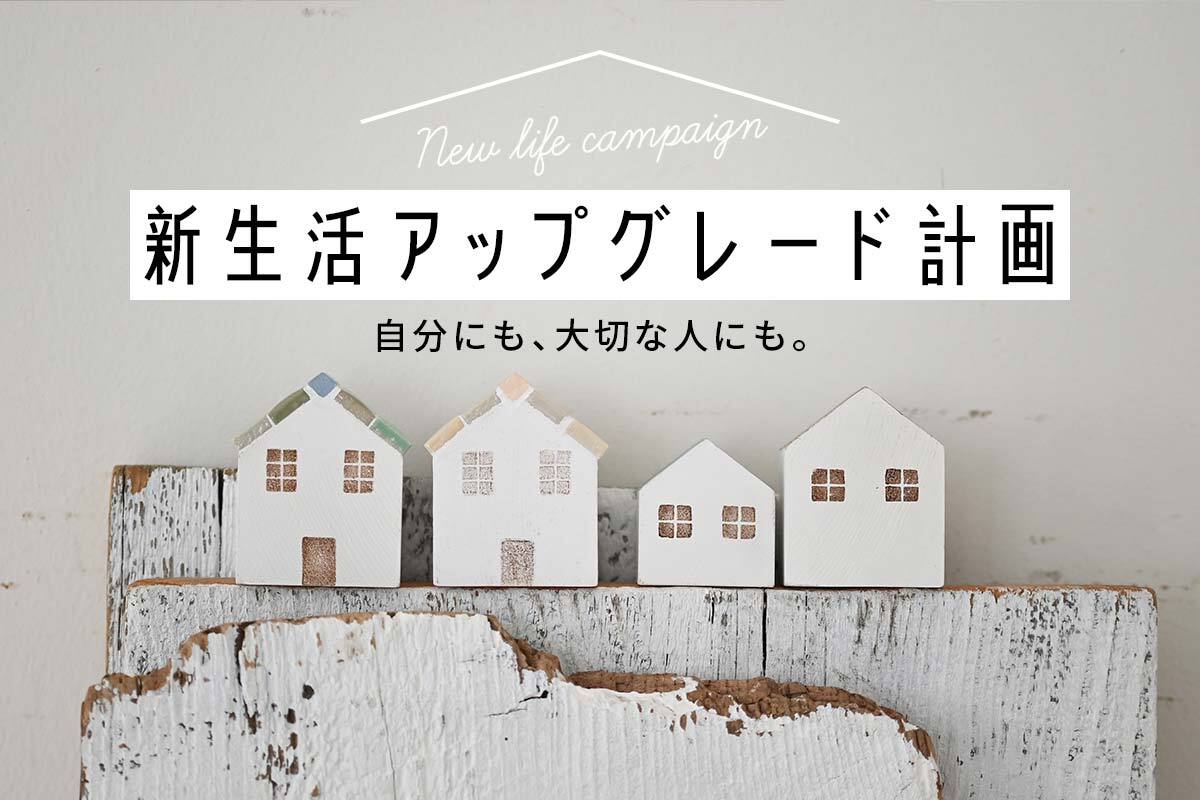この記事をシェアする
【ちょっと通になれる、北欧小話】No11:光をもたらす聖人、「聖ルチア」について
こんにちは。
突然ですが、おうちの電球や間接照明などを検討する際に、「ルクス」という言葉を見かけたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
明るさの単位であるルクスですが、実はこの言葉を由来としているのが、北欧諸国とも繋がりの深い光の聖人。今回ご紹介する「聖ルチア(ルシア)」なんです。
キリスト教の聖人、「聖ルチア」
聖ルチアは、3世紀末ごろにローマで実在したとされるキリスト教徒の女性です。
当時のローマではキリスト教は大変な迫害を受けていました。そんな中、異教徒との縁談を拒んだルチアは、キリスト教徒として告発されてしまいます。
信仰を捨てるか、命を捨てるか。文字だけでも目を覆うような拷問を受けても、彼女は決して信仰心を捨てることはありませんでした。
殉教者となった彼女はその強固な信仰心で人々から崇められ、いつしか光の聖人として愛されるようになったのです。
北欧の暗い冬を照らす、「聖ルチア祭」
聖ルチアは欧米ではそれほどメジャーな存在ではありませんが、北欧圏では広く信仰の対象となっています。
とても長く、寒く、そして暗い北欧の冬。「光」の名を冠する彼女にあやかりたいという、北欧の人々の願いが感じられますね。
そんな冬を楽しく、そして明るく過ごすために誕生したのが、毎年12月13日に行われる「聖ルチア祭」です。
古来より北欧では、旧暦の冬至に当たる12月13日に日の光を願う祝祭があったそうです。
ローマ生まれの彼女が北欧で信仰心を集めている理由は諸説ありますが、太陽を強く求める北欧の人々と、光の聖人である聖ルチアが密接に重なり合うことで、今の聖ルチア祭が誕生したというのが通説です。
聖ルチアをモチーフにした仮装も見どころ!
聖ルチア祭はクリスマスシーズンの1大イベントとして、大きな盛り上がりをみせます。
国によって内容が若干異なるものの、基本的な部分は同じ。ロウソクのついたリースと、白いローブを身に着けたルチア役の少女が、キャンドルを持った侍女たちを引き連れてパレードを行います。
このルチアの仮装は、地下牢に閉じ込められていたキリスト教徒に食料を分け与える際の、ルチア自身の姿をモチーフにしているといわれているんですよ。
近年では男の子も楽しめるよう、とんがり帽子に星のスティックを持った「星の少年(子供)」のコスチュームも定番化しているそう。
もっとラフなものだとジンジャーマンやサンタさんなど、ちょっとした仮装パーティのように楽しむこともあるんですって!
⇒「<★te-nori限定>ノルディカニッセ クリスマスツリーを持ったてのりサンタ(お星様) ライトアップ」はこちら
ナポリ民謡「サンタ・ルチア」
聖ルチア祭では、子どもたちによる合唱も見どころのひとつ。その中でも「サンタ・ルチア」は耳馴染みのある方も多いのではないでしょうか。
実はルチアはキリスト教の聖人であると共に、ナポリの船乗りの守護聖人としても大切にされているんです。
そう、聖ルチア祭で歌われる「サンタ・ルチア」は、私たちの知るナポリ民謡「サンタ・ルチア」を元にしたものだったのです。
ナポリ版「サンタ・ルチア」は、サンタルチア港の美しさを描写した爽やかな歌詞ですが、スウェーデン版は暗い冬を歌った全く違うものになっています。
ルチアを通して繋がる、ナポリと北欧。私は授業で習ったナポリ版の歌詞をかろうじて歌うことが出来ますが、皆さんは習ったことはありますか?:)
⇒「ノルディカニッセ 寝転がるサンタ サイレントナイト」はこちら
久しぶりの北欧小話、お楽しみいただけましたでしょうか:)
日本にいると太陽の光は当たり前になってしまいますが、例えばフィンランドの首都ヘルシンキでは、冬至の日照時間がおよそ6時間しかありません。
そんな日々が何か月も続く彼らにとって、聖ルチアはまさにすがりたくなるような存在だったのかもしれませんね。
te-noriでは、聖ルチア祭の本場スウェーデンで作られた、本物のルチア人形をご用意しております。
聖ルチア・侍女・星の子供と3品からお選びいただける聖ルチアシリーズは、特にクリスマスシーズンにはすぐに売り切れてしまう人気アイテム。
今回の小話でご紹介した通りのデザインになっていて、日本にいながら聖ルチア祭の雰囲気をお楽しみいただけます。
クリスマス以外でも楽しめる作りになっていますので、是非在庫のある今のうちにご覧くださいね。